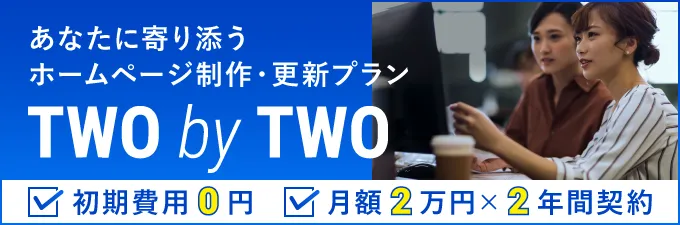僕は絵が「描ける」方に属するかと思うのですが、昔から周りの人と温度差を感じてきたことがあります。
それは、多くの人が絵を「描ける / 描けない」という二元論で話をすること。
実際には、両者の間はかなりのグラデーションがあります。
絵が比較的得意な人にも得手不得手があるだろうし、「苦手だ」と言いながらそこそこ上手いじゃないかと感じる人もいます。
今回は僭越ながら、絵を描くときの僕の頭の中について書いてみようと思います。
描ける・描けないの境目
先日、知り合いのFacebookに、猫と犬の写真が投稿されていました。
こんな感じの写真
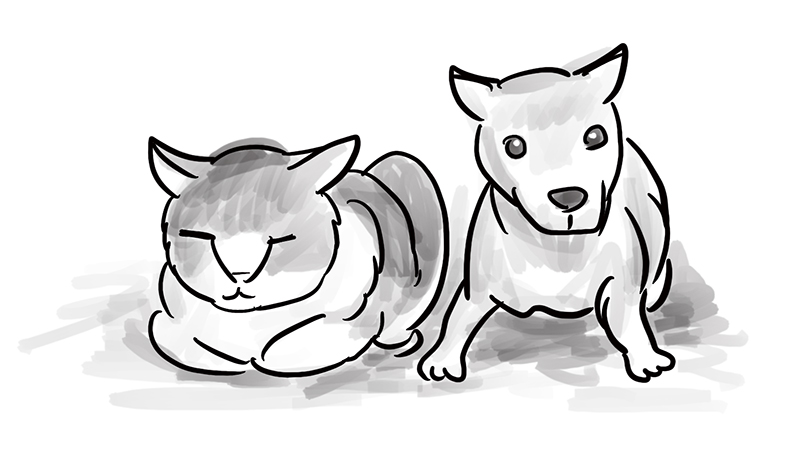
中学校の頃から十数年、実家で芝犬っぽい雑種を飼っていました。
そのため、同じような犬種であれば、どんなポーズだろうとどんな角度からであろうと、それぞれの部位の柔らかさ硬さまで、頭の中にリアルに思い浮かべることができます。
一方で、僕は猫がどうしてもうまく描けない。
昔から苦手な一つだったんです。
犬と猫はずいぶんと骨格が違う。
特に、前足が特徴的。
犬と猫が並んで同じポーズをする様子を、人生で初めて写真で見たので、その違いを改めて感じることができたんです。
絵を描く方程式
先ほどの絵を見てこう思った方、いないでしょうか。
「猫が描けない」と言いつつ、猫を描いてるじゃないかと。
本題はここです。
僕は、絵を描くという行為を大きく2つの動作に分解して考えています。
絵を描く=「①形をイメージする」+「②それを表現する」
僕は、「②表現する」はある程度できる。
しかし猫については、「①形のイメージ」が弱い。
ただ今回は、「①イメージ」は写真という形で提示されているので「②表現する」ことができたんです。
この構造に行き着いたのは、小学生の頃。
思いっきり世代感が出ちゃいますが、当時男子の間でアニメ『キン肉マン』を描くのが流行ってました。
僕もよく描いてましたが「上手い」と言われるたびに心の中で反論していました。
「こんなの、すでに絵になってるものをただ真似して表現してるだけじゃないか」と。
みんな、「自分がよく知ってるもの」を「きれいに再現できること」を「絵がうまい」と言ってるんだなと、冷めた目で見ていたのを覚えています。
それをなんとか伝えようと試みましたが、当時の僕のボキャブラリーでは無理だったことも思い出しました。
絵=観察+練習
絵を描く=「①形をイメージする」+「②それを表現する」
ずっと、この①と②は明確に切り分けてとらえてきました。
絵に関する書籍を見ても、これは「②表現」だけの内容だ、とか。
「②表現」は、練習ができるんです。
真似もできるし、道具によっても変化する。
しかし、「①イメージ」は意識してないといけない。
背景となる知識も求められるでしょう。
これ、動画撮影なら、
①ディレクター+②カメラマン
に例えられるかもしれません。
「①イメージ」を固めるためには、ただ「目に入る」だけではダメで、観察しないといけないんです。
対象の形を覚えたり、構造を知る必要がある。
冒頭の猫の例。
写真検索すると、こんな2種類の猫の様子が見つかりました。
前足の感じが違う。
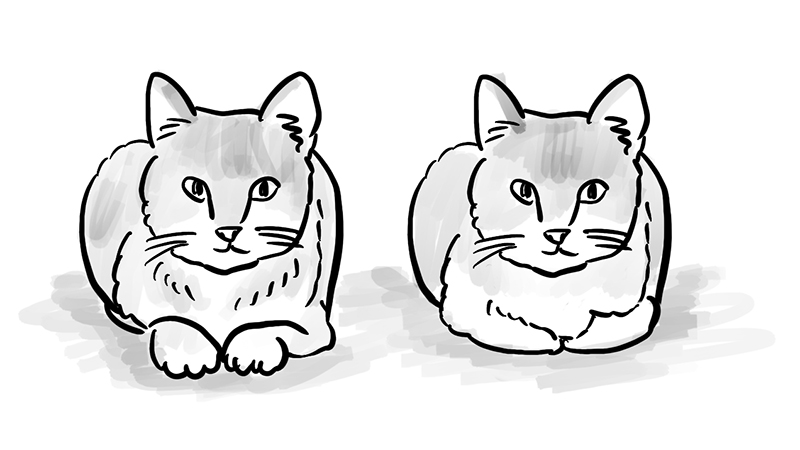
猫と親密な関係を築いたことがない僕には、どんな時に猫がこの違いを出すのかがわからない。
イメージできる・できない
こういった観察に、動物や昆虫は適していると思います。
誰もがイメージできて、かつ構造も調べやすい。
猫が描けるようになると、自然とトラやピューマも描きやすくなるでしょう。
「①イメージ」については、「誰もが同じものをイメージできる」ことが重要です。
例えば、「泳ぐゾウ」を描いてみます。
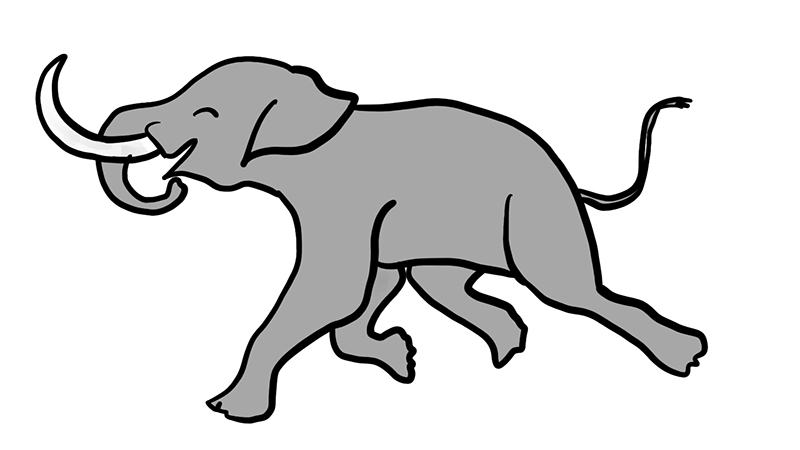
これを見て、どんな感想をもつでしょうか。
「上手いねえ」ではなく、「こんな感じで泳ぐの??」と疑問が生まれるはず。
「これはそもそも正しいの?」と。
ちなみに、写真を検索して見て描いたので正しいと思ってます。
泳ぐゾウを真正面から撮った写真もありましたが、それはもはや、泳いでいるのか暴れているのかよくわからなかったので不採用。
誰もイメージできないものを描いても、うまいのかどうか正しいのかどうか判断がつかないのです。
映画『エイリアン』に登場する宇宙生物の造形など、この世にないものはどうでしょうか。
最初に、ギーガーによるエイリアンのデッサンを見たリドリー・スコット監督はおそらく、「上手いねえ」ではなく、「これだよこれ!」という発見したような感想を口にしたことでしょう。
存在しないものを表現する力。
これこそ、僕は最大級の賛辞を贈られるべきだと思います。
苦手だけど「描きたい」とき
こんな細かいこと、どうでもいいと感じる人もいるかもしれません。
しかし、こういう小さい積み重ねが結果を左右していきます。
道具のイラストなら、持つ柄の場所によって力の入れ具合の印象も異なってきます。
持ち方によって、プロかアマかも伝わるでしょう。
「絵が苦手だ」という人もいるかと思いますが、表現するのが苦手なのか、観察することならできるのか。
その辺りが分岐点になると思います。
苦手なパートだけ人にお願いする、分業する。
そういう考え方もできますね。
歌うのは好きだけど作詞作曲はできない、みたいな感じでしょうか。
「②表現方法」の情報はたくさん溢れています。
でも、「①イメージ=観察」は個人的なもの。
何に興味を持つのか、どこが気になるのか。
ここもまた、絵の楽しみ方の一つではないかと思うのです。