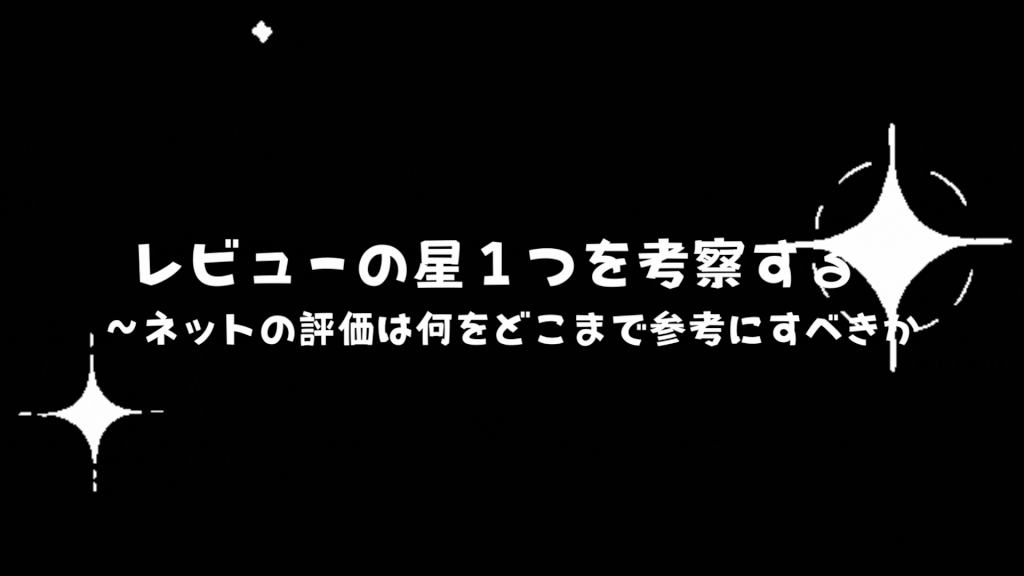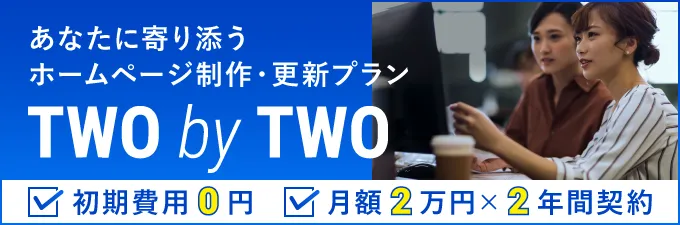「なんか違う」「サイコーです」
「こいつわかってない」「すごく分かりやすかった」
「なんだこれ」「すご」
僕は日々、ネット上でこういう声を全身に浴びながら生きています。
情報発信をしていくことのメリットは多いのですが、その代わりに「評価にさらされ続ける」ことを覚悟しなければなりません。
今はどんなものにも高評価ボタンと低評価ボタンがついている時代。
何かを発信すると、全く正反対の意見が出るのは当たり前。
想像もしてなかった反応もよくあります。
そんなとき、誰のどんな意見なら聞くべきなのか。
どの意見を採用すれば、今後に役に立つのか。
2001年5月5日にネット上で発信を始めた日から、これをずぅっと考え続けてきたのです。
星1つは<怒り>
『平和』の対義語は「戦争」ではなく『混沌』である。
みたいな表現をするなら、『評価が高い』の反対は「評価が低い」ではなく、『無関心』じゃないかと思うのです。
僕が映画や本を読んでがっかりしたときは、さっさと忘れるようにしています。
特段どこかに「あれひどい」などと書き込もうとは思わない。
(友人知人と雑談のネタにすることはある)
となると、ネット上にわざわざ星1つをつける、マイナスなコメントを書き込む、という行為には別の意図を感じるんです。
それは、<怒り>です。
定義が統一されてない
5段階評価って、評価基準が人によってバラバラだと感じます。
(A)基準が5。気に入らないことがあれば減点していく
(B)基準が3。良いなら加点、悪いなら減点していく
だから星3つを見て、「まあ普通だったか」と考えればいいのか、「あれ、なんか問題あったかな」と考えればいいのか、判断も困る。
余談ながら、僕の好きな年末のお笑いのM1グランプリでは、審査員たちは(B)を採用しているように思います。
1組目は(100点満点のうち)85点くらいにして、他の組には「さっきよりも面白かったから」みたいなコメントをしている。
星1つを掘り下げてみる
星1つのレビュー内容は重要です。
その内容から「なぜ星1つをつけたのか」を推測できるからです。
低い評価はつまり、それだけ期待値が高かったことを指すと考えます。
では何を期待したのか。そしてどう違ったのか。
僕は(今のところ)書かれたことがありませんが、
Amazonレビューに「詐欺だ」と書き込む人がいます。
人を騙すのに商業出版は割が合わなすぎるでしょう。
ただ、「自分にはできそう」と期待したのに「できなかった」ことが分かります。
映像の世界のAmazonレビューでは、「シナリオ」「絵コンテ」「写真(カメラ)」関連の書籍に、異様に厳しいコメントをする人が存在します。
「絵コンテ」は僕の専門の一つでオンライン講座は人気がある(受講者数が多い)一方、その分、星1つもよくちょうだいします。
(人気講座ほど平均評価は下がっていく、という現象)
僕の分析では、ターゲットから外れる人が多く受講している。
具体的には、「動画制作向け」の絵コンテ講座に、アニメーター志望が受講している形跡がある。
どれだけ注意書きをつけても、おそらく届いていない。
つまり、星1つからは逃れられない。
他の人はどう考えているか
こういった評価について、周りはどう考えているのか気になります。
そんな中、ある本に出会いました。
『絶対悲観主義』楠木健 著
大学で講義する著者の本で、はげしくうなづける箇所があります。
この先生はここが足りないとか、講義のこういうところが良くないとか、いろいろなコメントをもらいます。
「もっと多くの事例を使って説明してくれないと、具体性に欠ける」という人がいれば、「いや、もっと理論的なこととか抽象度を上げて説明してくれないと、実務の経験を持っている我々が勉強している意味がない」という人もいる。同じ人間が同じ講義を行なっているのに、正反対の評価が出てきます。どの声を聞いて、どの声は聞かないのか。取捨選択が必要になります。
これが本の出版となると、不特定多数の読者を相手にするわけで、いよいよ取捨選択が不可欠になります。
本を出すたびにお叱りを受けます。これは仕方がないことです。全員から受け入れられるということはあり得ません。「あ、こういう人からちゃんと嫌われている」という確認ができる。これが仕事にとても役に立ちます。
著者は「さっさとすぐできる答えを教えろ」という人から嫌われるのはいいことだ、と言います。
「特定の人からは嫌われていい」
これは当たり前のようで、でも言われないとウジウジしてしまうのが情報発信者ではないでしょうか。
僕は、初めての人向け映画制作ワークショップを18年開催していますが、集客で一番気を遣っているのは「対象外の人をいかに排除するか」です。
そもそも人の意見は参考になるのか
一つ一つの意見はすべて大事とも思いませんし、アンケート結果をすべて検討すべきはやりすぎだと考えます。
これは、「お客様は神様です」という言葉にも感じます。
神様どころかお客様ですらない人も存在すると思うんです。
『「みんなの意見」は案外正しい』
ジェームズ・スロウィッキー 著
この本ではタイトルが全てを言い切ってますが、<集合知>というものについて書かれています。
ただ、あくまである程度膨大なデータのもとでのことを言っています。
母数が少ない「みんなの意見」は、かなり偏りがあるんじゃないか。
「夢は人に話すといい」というのは自己啓発の世界で語られますが、僕は昔からイマイチ乗り気になれなかった。
応援してくれる人が見つかるメリットは理解できますが、それ以上に「やってどうするの?」「絶対無理だよ」といった否定的な意見にも遭遇しがちだからです。
だから、欲しい製品のAmazonレビューにせよ、自分の著書やオンライン講座の評価にせよ、数が少ないものは必ずしも正当な評価とは捉えないようにしています。
結局、何をどこまで気にすべきか
星の数とコメント内容が合ってない人もいます。
星1つなのにベタ褒めしてたり、星5つなのに批判してたり。
「配達についての文句」など製品に関係ないものもあれば、
ごく一部分を切り出して、全体を批判する人もいます。
すべての評価・コメントを同じ気持ちで受け入れててはつぶれます。
だから自分なりの評価の判断基準を決めました。
<評価の取捨選択マイルール>
・星5つはありがたいけれど、そのまま受け取らない。
・星2つから4つは熟読する。「こうして欲しかった」は宝石。
・星1つは別枠。内容を読んで改善点のみ取り入れる。
ノーコメントは、ノーカウント。
星の数は気にせず、コメントだけを読む、というのもいいですね。
一つでもひどいコメントがあると、気持ちが揺さぶられるもの。
こんな、批評しやすい世の中だからこそ、自分なりの判断基準を持つことが、発信を続けるために必要だと考えています。
あと、この記事に星1つはつけないでね。